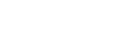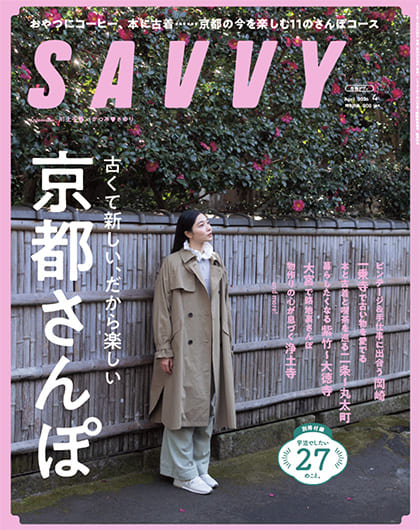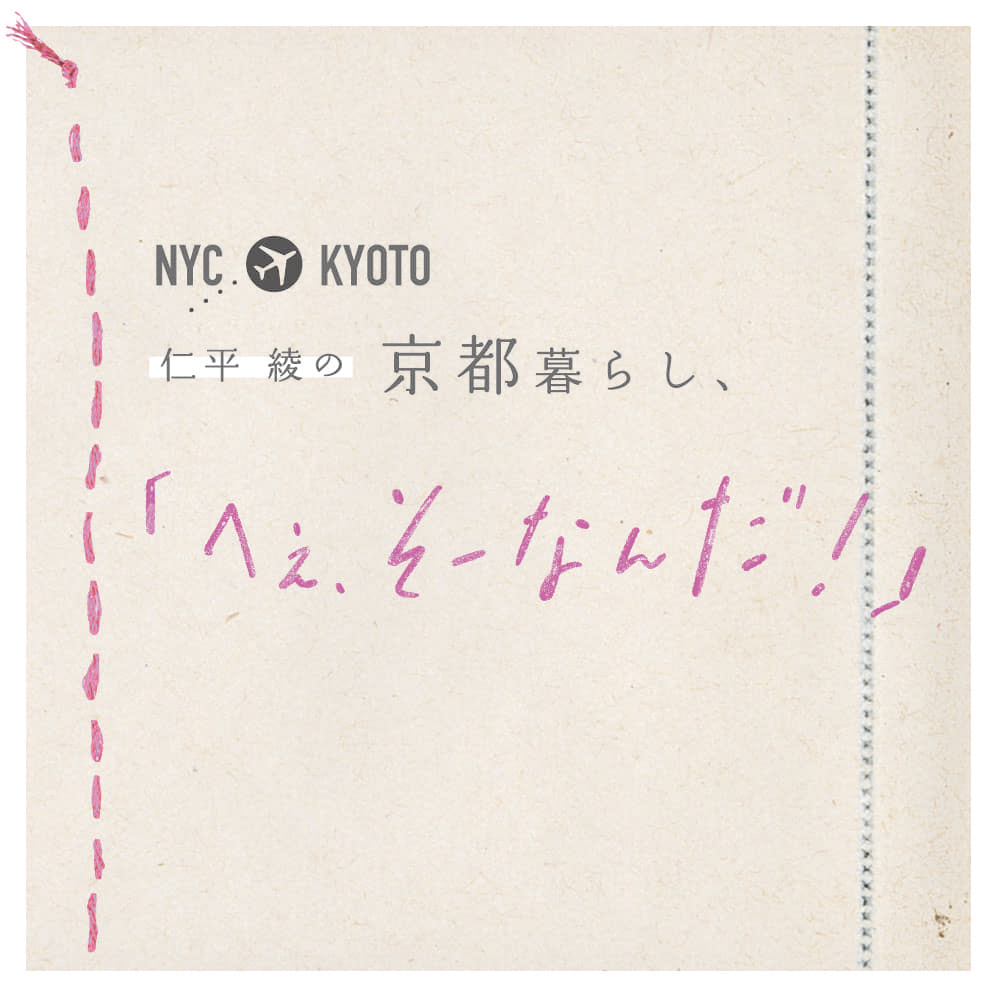ニューヨークから縁もゆかりもない京都に引っ越した
“よそさん”ライターが見つける、京都の発見あれこれ。
vol.21 木綿豆腐がやわらかい。
ある日、豆腐店で木綿豆腐を買い求めたら、“やわふわ”でびっくりした。カチッとした手応えはなく、表面の布目も控えめ。絹ごしと間違えた? と自分を疑ったほど。どうやら京都の木綿豆腐は、関東のそれとは違うらしい……。発祥となった店があると聞いて、嵯峨野へ向かった。
訪ねたのは、江戸後期創業の[嵯峨豆腐 森嘉]。六代目店主の森井邦夫さん曰く、四代目の祖父・進次さんが、やわらかな木綿豆腐の生みの親だという。第二次世界大戦中、戦地の中国で、にがりではなく、すまし粉(硫酸カルシウム)を凝固剤として使う豆腐づくりを目にした進次さん。日本に帰還後、にがりが手に入りづらくなっていたこともあり、すまし粉を用いた木綿豆腐を作るようになったそう。布を敷いた箱に豆腐をすくい入れ固める工程は変わらず。豆乳のたんぱく分だけを固めるにがりとは違って、すまし粉には「プリンみたいに」水分も一緒に固める作用があることから、ぷるぷるの木綿豆腐ができあがった。

嵯峨豆腐と命名し売り出したところ、「やわらかすぎて箸にもかからんと、当時は揶揄されたようです」と森井さん。ところが次第に評価され広まっていく。それに一役買ったのは、「お坊さんだった」という。寺の精進料理に欠かせない豆腐。[森嘉]は、嵯峨嵐山の天龍寺御用達として豆腐を納めていた。ネットどころかテレビもない時代、文化人と繋がりのあるお坊さんの口コミ効果は絶大だったらしい。懇意にしていた和尚が、[森嘉]のひろうす(がんもどき)を手土産で配ることもあったそうで(インフルエンサー!)、[森嘉]の豆腐はおいしいと噂に。かくして、京都ではやわらかな木綿豆腐が好まれるようになり、あちこちの豆腐店で作られ、今ではすっかり定着したというわけだ。

気になるのはその食べかた。私はもっぱら冷奴だけれど、森井さんは湯豆腐でもよく食べるとか。「火を通すと豆腐がゆるんで、また違う食感になる」とのことで、さっそく試してみたら、たしかに! 大豆の深い香りと甘みはそのままに、口当たりは、つるり、ぷるるっ。1╱2丁を秒で完食。食後は、森井さん推しの「冷奴の黒蜜がけ」に挑戦。水を切った嵯峨豆腐に黒蜜をかけると、台湾の豆花みたいな甘美なスイーツに変身。どちらもカチっとした木綿豆腐では食感が悪く、やわい絹ごし豆腐ではものたりない。その中間のような豆腐だからこそ叶う味だ。

ところで、京都の豆腐にまつわる謎があとふたつ。ひとつは、夏に販売される、からし豆腐。丸いドーム型で、海苔に包まれたからしが中に仕込まれている。発祥は岐阜らしいけれど、なぜ京都でも? 森井さんに聞いてみたところ、なんとまたしても発端は、祖父の進次さん! すごい。京豆腐界のパイオニアだったのだなあ。もうひとつ、油揚げがなぜ大きいのか?(関東の油揚げの2〜3倍はある)という謎は、森井さんもわからず(さすがに祖父、進次さん考案ではなかった)。規格なの? たくさん食べたいから? 解明にむけ、調査は続く……。


- 電話番号075-872-3955
- 住所京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町42
- 営業時間9:00〜17:00
- 定休日水&火不定(祝の場合は営業、翌日休)
- カード使用可
- 公式HPhttps://sagatofu-morika.co.jp/
- アクセスJR嵯峨嵐山駅から徒歩11分

Nihei Aya
エッセイスト。9年のN.Y.滞在を経て、2021年にあこがれの京都へ。近著に『ニューヨークおいしいものだけ』(筑摩書房)、『ニューヨークでしたい100のこと』(自由国民社)、エッセイ本『ニューヨーク、雨でも傘をさすのは私の自由』(大和書房)など。
- Instagram@nipeko55